認知症医療の権威である、長谷川和夫先生ご自身が認知症になり、わかったことや、伝えたいことを本書で書かれています。

今回は第1章についてまとめていきます。
第1章では
・認知症は誰にでも自然に起こり得る。
・恥じることなく公表する。
・理解を得て、普段どおりの生活を送る。
ということを伝えたいんだと思います。
認知症について不安に思っていたり、学ばれる
介護士さん
ご家族様
ご本人様
に、ぜひ読んでいただきたい本ですので、記事をお読みになって、読んでみたいと思っていただけましたら、ぜひ、手にとって見てください。
長谷川先生は、
認知症=特別なものではない
認知症=別人になるではない
ということをおっしゃっています。
本を読む機会がない、読む時間もないという方の為にまとめました。
たくさんの方に、認知症について、知っていただければ幸いです。
どうやら認知症
家の鍵をかけたか確認してもあやふやで確信が持てない
日付曜日がわからない
「実は認知症なんですよ。でも普段通り生活してますよ」
ご自身の講演会で自然に出てきた言葉だそうです
大事なことを伝えたい気持ち
人事ではないと言うことをが自然に出てきたんだと思います。
認知症になることは「ヒトゴト」ではない
長谷川先生の言う大事なことっていうのは
誰もが認知症になる可能性があり、自然なこと
認知症になっても人である
人生100年時代という長寿時代で
誰もが向き合う必要がある
普通の生活を送ることが大事
だということ
誰もが認知症になる可能性があり
長寿時代で誰もが向き合う必要がある
と言うことは、つまり
人事ではないんだよと言うこと
認知症になるのは当たり前と思った
ショックだったかと聞かれて答えた発言です
「少なからずショックだったけどなったものはしょうがない」
と考えることができたそうです
しかし、これは長年認知症医療に携わっていたことからこう思えたのかもしれませんし、もともとの性格もあったのかもしれません。
長谷川先生は受診に来られた患者さんに対して
「何も答えられなかった」
と言っています
それは何故かと言うと、【生半可な慰めは通用しない】と思ったからだそうです。そして、『僕も一緒に悩みますよ。』と心の中で思い
手を握り続けたそうです。
なぜ公表したのか?
認知症についての正確な知識
認知症の人への接し方
認知症を理解して支える存在やその仕組みが絶対に必要
と思ったからだそうです。
さらには
自分自身がよりよく生きていくため
ともおっしゃっています。
これは認知症の
【ありのままを伝え、少しでも人様や社会のために役立つ】ことをしたい
という思いがあったからだそうです。
嗜銀顆粒性認知症(しぎんかりゅうせいにんちしょう)
長谷川先生はこの嗜銀顆粒性認知症だと診断されています。
このタイプの認知症は
80歳代など高齢になってから現れやすく、進行が緩やかです
長谷川先生は80歳を過ぎてからなる認知症を晩節期の認知症と呼んでいます。
この 晩節期の認知症 になる人っていうのは
これからどんどん増えていき、絶対に人事では無い
ということを知っていただきたいとおっしゃっていました。
なかなか耳慣れない言葉というか、あんまり聞いたことがないというか、むしろ私は、全然聞いたことがなかった認知症の種類です。
勉強不足なのかとも思いましたが、知りえる機会が少ないなあとも思いました。
周囲のサポート
理解力や判断力が弱っていき、それらを補うために
周囲のサポートが必要
家族等のサポートがあり、何とか普通に近い暮らしができているとおっしゃっていました。
「認知症は恥ずかしいと思わせてしまうような社会であってはいけない。」
認知症の進行により、普段できていた配慮も少し欠けてしまうことがあったそうです。
そこで先生は反省されたと言っています。
「認知症を恥ずかしがったり隠そうとするような社会であってはいけない」
これは、つまり
「自分は認知症なんだよ」と周囲に言って
認知症であると分かってもらった上で今まで通りに付き合っていける
そんな社会になって欲しい
ということなんです。
「人生100年時代のこれから、認知症は誰にでも、自然に起こることであり、向き合うこと。恥じたり隠すことなく、公表し、理解してもらったうえで、普段どおりの生活を送るべきだ。」
繰り返しですが
・認知症は誰にでも自然に起こり得る。
・恥じることなく公表する。
・理解を得て、普段どおりの生活を送る。
ということを第1章では伝えたかったのではないでしょうか。
では、今回はこの辺で。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
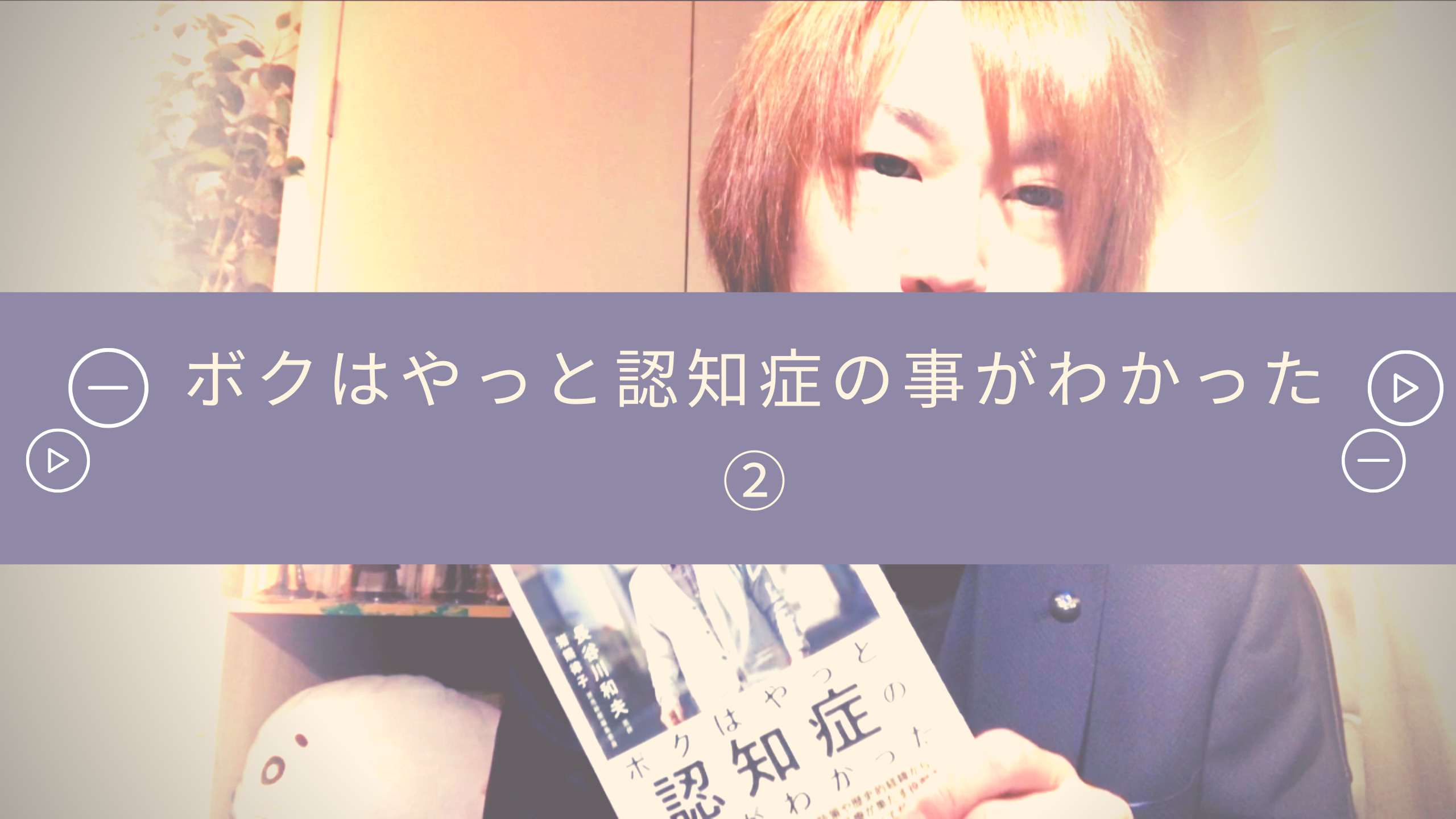

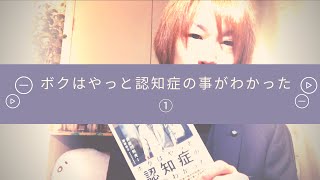
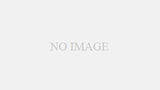
コメント