
認知症について、あまりよくわからないよ。という方のため
認知症について、地域の方に理解していただくため
認知症サポーター養成講座を、講師として開かせていただいています。
講座のご要望がありましたら、ご連絡ください。
今回はその内容について、簡単にまとめていきますので、ご参考にしていただき、興味を持っていただければ幸いです。
また、認知症サポーターキャラバンメイトの方が、講座を進める上でも、参考になるかと思います。
【認知症の基礎】
認知症サポーターとは?

地域や職域・学校などで認知症の基礎知識について、またサポーターとして何ができるかなどについて学び
認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る応援者のことです。
認知症とは?

さまざまな原因により脳細胞が死んでしまったり、働きが悪くなって
記憶・判断力などに障害が起こり
およそ6ヶ月以上継続して 日常生活に支障をきたしている状態です。
認知症の種類

・アルツハイマー型認知症
・レビー小体型認知症
・脳血管性認知症
・前頭側頭型認知症
アルツハイマー型認知症の特徴
・認知症患者の全体の 約50% にあたる。
・脳の細胞がゆっくりと死んでいき、脳が委縮する。
・記憶の障害 ・ 見当識障害 ・ 妄想 ・ うつ
レビー小体型認知症の特徴
脳の神経細胞の中に「レビー小体」と呼ばれる
異常なたんぱく質の塊
が大脳に広くに現れる。
- パーキンソン症状(手足の震え、引きずる様な足取り)
- 認知機能障害、幻視、抑うつ
脳血管性認知症の特徴
- 脳梗塞や脳出血などによって発症する認知症
- 手足のしびれ、麻痺
- 認知機能障害(高次脳機能障害)
予防効果が高い。
前頭側頭型認知症の特徴
- 脳の司令塔役である前頭葉が障害される。
- 我慢や、思いやり 社会性が失われる。
“ わが道をゆく ” 行動をとる
*前頭葉…感情や、意欲などを司っています。
【認知症の症状】
大きく分けると
- 中核症状
- 周辺症状(BPSD)
の2つあります。

中核症状とは?

- 記憶障害
- 見当識障害
- 理解・判断力の低下
- 実行機能の低下
のことを言います。
これにより
現実を正しく認識できなくなります。
脳の細胞が壊れることによって直接起こるため
「治りにくい」
記憶障害

新しい情報をキャッチできませんが、昔の記憶は覚えています。
そして、記憶障害は行動そのものを忘れてしまいます。
見当識障害

『時間』や『季節感』『場所』や『方向感覚』
自分の置かれている状況を理解する力が低下します。
理解・判断力の低下

- 考えるスピードの低下
- 2つ以上の事が重なると同時に行えない。
- 予定以外の出来事に混乱しやすくなる。
- 詐欺被害などの危険
目に見えないメカニズムが
理解できなくなります。
実行機能障害

目標→計画→実行→効率化・調整
などの一連の活動を行うことができなくなります。
手助けをしてくれる人がいれば
その先は
自分でできる
ということがたくさんあります。
「できないから、やらせない」のではなく
一緒に行うなどして、孤独を感じさせないで欲しいと思います。
周辺症状・BPSD

うつ状態や妄想のような
精神症状や
日常生活での
行動上の問題
が起こる。
「性格」
「環境」
「人間関係」など
さまざまな要因がからみ合って起こる症状です。
認知症の進行によって悪化するばかりでなく
周囲の人の
不適切な対応によって悪化します。
しかし
適切に対応することで
進行を抑制し、改善できます!
【認知症のサイン・治療・予防】
認知症のサイン

- 憂うつ
- 外出をいやがる
- 気力がなくなった
- 被害妄想がある
- 話が通じなくなった
- 外出すると迷子になる
- お金の勘定ができなくなった
サインを見逃さず、専門機関に相談しましょう。
相談のタイミングは早いほうがいいです。
MCI(軽度認知障害)

認知症の予備軍(入り口)
そのままにすると
年間1割以上の方が認知症に進行していきます。
早期発見・早期治療が重要
治療方法は?

認知症を完全に治す治療法はまだありません。
治療目的は、できるだけ
症状を軽くして、進行の速度を遅らせる
ことです。
中核症状に対しては
一時的ではありますが、効果のある薬があります。
周辺症状に対しては
まずは薬に頼らず
ストレスとなる状況などの環境整備や
運動や回想法などの認知機能訓練
などから行います。
いずれにしても
早期発見、早期治療
が重要 です
認知症の予防
認知症の予防 = 認知症発症のリスクを少なくすること
予防をすることで、認知症にならないというわけではありません。
・規則正しい生活
・食事
・運動
・口腔ケア
(歯磨きだけでなく、義歯があっているか?も重要です)
などをしっかり行うこと。
付け加えて、重要なことは
睡眠の質を上げること
だと私は思います。
予防のほとんどが、自律神経を整える習慣と同じです。
自律神経の乱れ=認知症発症のリスク
ともいえるのではないでしょうか?
自律神経を整える

【認知症の方への接するときの心構え】
実際に認知症の方と接する際の注意点
- 「認知症本人に自覚がない」は大きな間違い
- 「私は忘れていない!」に隠された本心がある
- 周囲の人は、「こころのバリアフリー」を
認知症を理解したうえで
「自分だったらどう生き抜くか?」
健康な人の心情がさまざまであると同じように
認知症の人の心情もさまざまです。
さりげなく、自然に
それが一番の援助です。
具体的な場面や、見守る為のポイント
迷っている高齢者を見かけたとき
- 名乗る
- 正面から、目線の高さで、ゆっくりと
- ゆっくり待ち、否定せずに安全地へ
明らかにおかしな話しをされる方への接し方
- 否定しない
- 即実行・行動をしない
思いつき不安や勘違い不安があります。
一つ一つに、すぐ反応・行動をせずに
まずはゆっくり話しをきいてみてください。
そして
「大丈夫かな?」と
みんなが少しづつでも気にかけてくださるだけで
地域が変わり
高齢者、認知症の方が
住みやすい町
になっていきます。
【家族の気持ちの変化】
認知症の方のいる、ご家族様の気持ちの変化

地域の方の目としては、ご家族がいろんな悩みを抱えていることをわかっていただければと思います。
「追い込まれて、感情の表現がうまくできていないのかもしれない」とわかっていただきたいのです。
【認知症の方への基本姿勢】
対応心得3つの「ない」
- 驚かせない
- 急がせない
- 自尊心を傷つけない
自分がされたら嫌なことは
認知症の方でも一緒
ということを、覚えておいてください。
具体的な対応の7つのポイント
- まずは見守る
- 余裕をもって対応する
- 声をかけるときは1人で
- 後ろから声を掛けない
- 相手に目線を合わせて、優しい口調で
- 穏やかに、はっきりした話し方で
- 相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する
基本的な意識としては
「不安感を取り除いてあげる」ことで、つまり、
安心していただくことです。
最後に
「不安なんだから助けてあげなきゃ!」と肩肘を張る必要はありません。
むしろ、その意気込みが、認知症の方を圧迫してしまう可能性もあります。
「認知症の方は不安要素が多いんだな」
と理解していただき
さりげなく、やさしく声をかけてくださるだけでも
見守っていただくだけでも
充分だと思います。
人生100年時代
誰もが認知症になる可能性があり
誰もが認知症と向き合う必要があります。
怖がったり、特別なことなど思わずに
みんなで向き合っていきましょう。
前述しましたが
認知症サポーター養成講座を、講師として開かせていただいています。
講座のご要望がありましたら、ご連絡ください。
-SNS-
ツイッター
https://twitter.com/ryzirrxdb
フェイスブック
https://www.facebook.com/tsutsumi.kazuhiro.33
インスタグラム https://www.instagram.com/tsutsumi.kazuhiro.33/?hl=ja
もやっておりますので、こちらからでも、ご要望お待ちしております。
認知症関連
認知症と自律神経
予防のほとんどが、自律神経を整える習慣と同じです。
自律神経の乱れ=認知症発症のリスク
ともいえるのではないでしょうか?
自律神経を整える




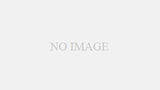
コメント